未来の薬剤師を育てる――。
薬局にとって実習生の受け入れは、大きな意義を持つ取り組みです。
指導薬剤師という役割は、現場経験を伝える“バトンランナー”として、
誇りある立場だといえるでしょう。
しかし一方で、薬学生の声に耳を傾けると、
「しんどかった」「つらかった」「面白くなかった」など、
ネガティブな感想も少なくありません。
その声はやがて、薬局の口コミや評判、さらには将来の人材確保にも影響していきます。
できることなら、薬学生には「来てよかった」と思って帰ってほしい。
そう思う薬剤師さんも多いはずです。
そこで本記事では、これまで数々の実習生と向き合ってきた私が、
“楽しくてタメになる実習”を実現するための指導のコツを、具体的にご紹介します。
指導薬剤師になりたてで不安な方や、「実習がうまくいかない…」と悩んでいる方は、
ぜひ参考にしてください。
薬学生の声|実習がつらい!その理由。薬局実習へのリアルな不満
薬学生にとって、薬局実習は“現場デビュー”のような楽しみと緊張が入り混じる時間です。
ですが現実には、「つらい」「しんどい」「行きたくない」といったネガティブな声も多く聞かれます。
実習経験のない指導薬剤師も少なくないため、
まずは実際に寄せられている学生の声から振り返ってみましょう。
私が学生の頃の友人や、向き合ってきた実習生、前職のスタッフなど、
周りの人から聞いた話を元によくある事例をご紹介します。
放置されて投薬できない
特に多いのが「忙しさの中で放置されてしまい、何もさせてもらえなかった」という声。
実は私自身も、実習中に一度も投薬をせずに終わった経験があります。
他の面では充実していたため私は満足感を持てましたが、
こうした放置が実習全体を“意味のないもの”に感じさせてしまうケースは少なくありません。
ピッキングと服薬指導はやったけど、ただ繰り返すだけ
ピッキングや服薬指導といった薬局業務を経験しても「作業をこなすだけで終わった」と感じるパターン。
こちらもかなり多い事例です。
薬学部では“臨床で役に立つ薬剤師”を理想像として学ぶため、期待して臨んだ実習で、
実習が単なる流れ作業に感じられると、理想と現実のギャップに落胆してしまうのです。
理不尽な物言いで自己肯定感を下げる
「邪魔」「早くしろ」「全然できてない」といった、高圧的な物言いも一定数存在します。
こうした言葉が、実習生の自己肯定感を著しく傷つけてしまうケースもあります。
たしかに、薬学生の知識や準備が足りない場面もあるかもしれません。
それでも彼らは“学びに来ている立場”です。できないからこそ、実習を通じて学ぼうとしている。
その前提を忘れた指導は、モチベーションを失わせる“教育事故”になりかねません。
薬学生の”実習がしんどい”を理解する|指導者との感覚のズレ
薬学生の声を見てきたところで、
次は「なぜ学生はしんどいと感じるのか?」を掘り下げてみましょう。
どんなに意欲的な学生でも、実習とは少なからずストレスを感じるものです。
この章では、その“しんどさ”の正体を指導者の視点で紐解いていきます。
学生にとって慣れない環境
そもそも、慣れない環境に身を置くこと自体がストレスになります。
特に、普段は座学中心で過ごす学生にとって、慌ただしく動き続ける現場はまったく別世界。
忙しい場面ではスタッフに質問するタイミングすら見つけられず、
「自分、邪魔になってないかな…」と不安になる学生も少なくありません。
周りの大人に気を遣う
薬学生も「自分は外部から来たお客さんだ」という自覚を持っています。
働くわけでもなく、むしろ教えてもらう立場。
手間をかけさせているという負い目を感じているのです。
実習中は、“嫌われないように”空気を読み、“邪魔にならないように”慎重に動く学生が大半です。
この継続的な気遣いが、じわじわと精神的な負担になります。
理想と現実のギャップに苛まれる
勉強してきた学生ほど、「自分も役に立ちたい」と強く思っています。
でも、現場では知識だけでは対応できないことが多く、思うように力を発揮できないことも。
質問に答えられない、ミスしてしまう、役に立てない──
そんな経験が続くと、“自分には向いていないのでは”という無力感すら生まれてしまいます。
実習が“しんどい”のは、単なる甘えではありません。
学生が感じるプレッシャーや不安には、きちんと理由があるのです。
では、そんな中でも学生たちは何を期待し、どんな体験に価値を感じているのでしょうか。
次章では、薬学生が実習に求めている“リアルな期待”について紐解いていきます。
薬学生の実習への期待|薬学生にとって”大事なこと”は何かを解説
ここまで見てきた薬学生の声から、
彼らが実習にどんな“価値”を求めているのかが浮かび上がってきます。
この章では、薬学生が特に重要だと感じている体験や、
実習中に得たいと考えている成長について解説します。
服薬指導体験への期待|経験数が学生のステータス
「対物から対人へ」の流れの中で、服薬指導は薬局実習における最も“薬剤師らしい”体験
として、学生の期待値が非常に高い項目です。
実際、学生同士の会話でも
「いつから服薬指導をやらせてもらった?」「何件くらいやった?」
といった話題がよく出ます。
周囲と比べて進捗が遅れていると感じると、
「このままでいいのかな…」と不安や焦りにつながることもあるのです。
やらされ感と成長実感|カギは主体的な行動の喚起
実習が進むにつれ、薬の位置や業務の流れにはだんだん慣れてきます。
しかし、それでもピッキングしかできなければ、
それ以外の時間は“ただそこに立っているだけ”の状態に。
結果として、薬局がやるべき作業を学生に割り振る形になり、
「こなすだけ」の実習になってしまいます。
こうなると学生は“やらされ感”を抱くようになり、主体性が育ちにくくなります。
薬学生は一般的に真面目な人が多く、これまでの勉強を通じて「成長したい」という欲求も強く持っています。
そのため、自分なりの成長を実感できない実習では、やりがいを感じにくくなってしまうのです。
つまり、薬学生は単に「体験」することではなく、“意味のある成長”を求めて実習に臨んでいるのです。
次章では、そもそも薬局実習とは何を学ぶ場なのか、
改めてその目的を見つめ直してみましょう。
薬局実習の目標とは?薬局実習の本質と到達点
大学側から共有される「到達目標」は、主に定性的な能力に焦点が当てられています。
これは、評価基準に基づいて実習をチェックするための“指標”として必要なものですが、
実際の現場で得られる“本当の学び”は、それだけでは語りきれません。
現場体験の側面|現場と知識の繋がりを知る
もっとも見えやすいのは現場を体験するという側面です。
4年生までの薬学生は、基本的に机上で知識を身に付けるだけで実習まで現場を体験することはありません。
(1~2日の見学などは大学のイベントであったりもします)
実際の業務を通じて、「知識がどう使われるのか」「机上の学問と現場のリアルにどんなギャップがあるのか」
を体感する。これは薬局実習のもっとも基本的で、かつ重要な学びの一つだと言えるでしょう。
実習でよくある勘違い|誤った目標の設定
実務実習は“現場を体験する”ことがメインですが、周囲の学生と比べるあまり、
ズレた目標を立ててしまうこともあります。
たとえば「友達は毎日10人服薬指導してるらしいから、自分も簡単なやつだけでもやりたい」
という学生に、 私はこう言ったことがあります──
患者はお前のレベル上げのために存在してるわけじゃねーから。
※勿論、その子が対応していた数は決して少ない回数ではありませんでした。
あくまでもただ無駄に回数を重ねる必要はないと考えての発言です。
経験を積むこと自体はもちろん大切です。
しかし、実習は技術を磨く場でも 経験値を積む場でもありません。
大事なのは「回数」ではなく「気づきの質」。
指導者として、こうした誤解された目標を修正してあげることも重要な役割だと思います。
実習で本当に身に付けるべきは薬剤師としての「姿勢」と「考え方」
薬剤師は医療チームの一員として、患者の命と生活を支える存在です。
日本の医療制度が「国民皆保険」を採用しているのは、
誰もが経済状況に関係なく、必要な医療を受けられるようにするため。
その中で医療従事者に求められるのは、
この理念を体現する「姿勢」と、実践するための「考え方」です。
実習の本質は、こうした“医療者としてのあり方”の土台をつくることにあります。
指導者はその到達点を理解し、学生が無理なくそこに近づいていけるよう導く存在であるべきです。
次章では、こうした目標に向けて、薬局側がどのように学生の成長を支援できるのか。
実習指導の具体的なアプローチについて考えていきます。
薬局側が意識すべき3つの成長支援ポイント
実習の目標を理解したところで、では実際に何をすればそこに近づけるのか?
この章では、指導薬剤師が意識しておきたい“成長を支援する3つの観点”を紹介します。
挑戦させる|できないことにトライできる環境
実習で学生に“挑戦”させることは不可欠です。
というサイクルこそが、成長の原動力だからです。
そのためには、できないことに安心して取り組める環境づくりが必要です。
たとえば以下のような支援が有効です。
・失敗しても損害が出ないようなフォロー体制をつくる
・段階的にハードルを設定し超えさせる
・できるようになったことを任せて自己効力感を高める
また「何がわからないのかがわからない」段階では、質問を促しても出てこないのが普通です。
無茶振りではなく、実力より“ほんの少し上”の課題を与えることで、無理なく挑戦させましょう。
そして、課題を与える際には常に「できなくて当然」という前提で接することが大切です。
振り返らせる|自己評価+フィードバック
振り返りは、成長の質を高める上で非常に有効な手段です。
しかし、自分ひとりでうまく振り返れない学生も多いため、
指導者による仕掛けづくりが重要になります。
たとえば服薬指導を終えた後などは、まず「自分でどう感じたか?」を聞き出します。
ポイントは、指導者側の答えを押し付けず、学生が考えるプロセスを支援すること。
主体的に考えた答えだからこそ、学生の中に残り、次につながります。
意味づけさせる|課題抽出のための洗い出し習慣
学生の多くは、「問いには一つの正解がある」という一問一答的な思考に慣れています。
しかし実際の現場では、一つの症状や課題に対して、複数の原因・対応策が存在します。
そうした“多面的な視点”を育てるのに効果的なのが、洗い出しの習慣です。
具体的にはテーマを設定し、自分の知識や考えを言葉にして書き出させます。
それを見ながら、煮詰まっていたら「こういう場面ではどう?」と提示するのです。
以下に、実際にやらせたことのある洗い出しを一例として掲載します。
こうして「可能性の広がりに気づく力」を育てることは、
課題を“意味づけして捉える”力につながっていきます。
ここまで紹介した支援ポイントは、どれも効果的で意義のあるものです。
しかし、それらを現場の忙しさの中で実行することは簡単ではありません。
次章では、そんな“現実の壁”とどう向き合っていくか──
指導者に求められる姿勢について考えていきます。
忙しくても、向き合う覚悟を|薬局実習の“本当の指導”とは
実際のところ、ここまでの対応を日々こなすのは、正直かなり骨が折れます。
学生によって性格も知識量も異なり、得意・不得意も千差万別。
それに合わせて指導スタイルをチューニングする必要があるため、
現場では臨機応変な対応が求められます。
それを、普段の業務と並行して行うのですから、大変なのは当然です。
しかし、忘れてはならないのは──
学生は“社員”ではないということ。
判断力も責任も未熟な段階にあり、新入社員とはまったく違う視点で教育を考える必要があります。
時間と手間がかかるからこそ、教育者としての姿勢が問われます。
未来の医療を担う学生たちがどう育っていくのか──
それは、まさに指導者であるあなたの腕にかかっているのです。
まとめ|未来の医療を育てる、誇れる仕事として
以上、薬局実習の指導者に向けて意識すべきことをお伝えしました。ここまでのポイントを整理します
・実習への期待が裏切られることで、「しんどい」「つらい」と感じる学生は意外と多い。
・慣れない環境・気疲れ・理想とのギャップが、実習をしんどく感じる主な要因。
・薬学生は成長を実感できる体験や、自らの役割を感じられる実習を求めている。
・薬局実習の本質は、知識と現場をつなぎ、薬剤師としての姿勢と考え方を育てること。
・挑戦、振り返り、意味づけの3つの支援が、“やらされ感”から“学び”に変えるカギ。
・学生は社員ではない。だからこそ、教育者として向き合う覚悟と姿勢が求められる。
実習の指導には手間も時間もかかります。
しかし、学生の成長を間近で感じられる貴重な機会です。
実習が「しんどい場」ではなく「成長の場」となるかどうかは、
現場の工夫と指導者の姿勢にかかっています。
はずれ薬局と呼ばせないために──
あなたの指導が、薬学生の未来を大きく左右するのです。
以下の記事では、実習生向けの記事として「実習で怒られる事例」とその「理由」
について解説しています。
指導者の方も、怒りたくなる感情の言語化に是非お役立てください▼
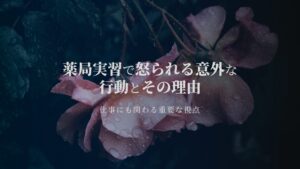



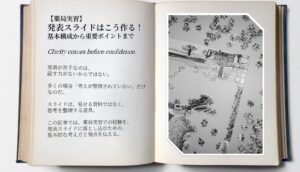
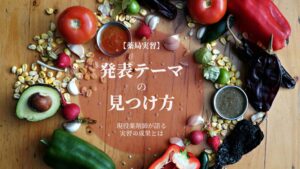

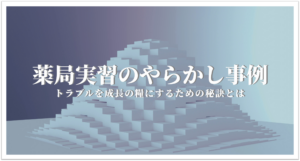
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 【薬局実習】薬学生のしんどいを防ぐ!ハズレ薬局認定を回避する方法 […]