薬局実習にも慣れてきた頃に意識し始めるのが成果発表。
何をテーマにするべきか、お悩みの学生さんも多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな薬学生の皆さんに向けて、数々の実習生の発表制作を支援してきた私の経験から、
成果発表のテーマの選び方を解説します。
なお、「発表スライドの作り方」については別記事で詳しく解説しています▼
【薬局実習】発表スライドはこう作る!基本構成から重要ポイントまで│Formulø
どうせ発表するなら指導者を唸らせるような発表を考えたいという方はもちろん、
とりあえず面倒なことはさっさと終わらせたい、という方にも役に立つような成果発表のヒントをお届けします。
実習の成果を明確に|実は知らない”報告すべき内容”
発表テーマの選び方について説明する前に、まずは知っておいて欲しいことがあります。
それは、そもそも実習の「成果」ってなんだろう?ということ。
多くの実習指導者もここを明確にしないので、学生側はテーマを決める軸が定まらないのです。
まずは成果が何を指すのかを順を追って解説します。
実務実習の目的|何をする期間なの?
まずは実習はどこに目的があるのかを確認していきましょう。
文部科学省の「薬学実務実習に関するガイドライン」では、以下のように記載されています。
実習は、それまで薬学部で学んできた知識・技能・態度を基に臨床現場で「基本的な資質」の修得を目指し、
実践的な臨床対応能力を身に付ける参加・体験型学習である。
引用:薬学実務実習に関するガイドライン
また、この“基本的な資質”については「薬学教育モデル・コアカリキュラム」の中で、
以下のような項目に分けて定義されています。
・医療人としての使命感・倫理観
・患者/生活者本位の視点
・チーム医療への参画力
・薬物療法を実践するための知識と技術
・地域連携、研究、教育、自己研鑽への姿勢 など
引用:薬学教育モデル・コアカリキュラム(平成25年度改訂版)
……と、難しいことが書かれていますが、すごく簡単にまとめると、
「医療人としての心構え」と「薬剤師としての基礎的な力」を現場で体験を通じて身につけましょう
ということです。
成果の捉え方|ゴールに対する達成状況
このゴールを踏まえると成果として何を求められているのかがわかりやすくなります。
実習の成果とは、すなわちこうしたゴールをいかに経験し達成したか、ということなのです。
例えば仕事ならば「売上目標があってそれを120%達成しました」というと、目標よりも1.2倍の売上を作った、
という成果になるわけです。
ただ、この小難しいコア・カリキュラムを読み込んでゴールを明確にしよう、などというつもりは毛頭ありません。
大事なことは、薬剤師としての「基本的な資質」を身に付けることが実習の目的であるということ。
つまり、実習の成果とはこの「基本的な資質」をどのくらい身に付けたか、だと理解できます。
薬局実習に特有の成果|現場から見た実習生の成果とは
もっと簡単に言えば、実習の中で経験したことを通して、
自分が「成長したな」と思うことを教えて欲しいということなのです。
現場側からすると、実習生はスタッフではないので売上などの金銭的な価値としての成果は全く求めていません。
そこが新入社員教育とは異なるところ。
むしろ、「最初は何もわからなかったけれど、経験を通じてこんなことに気づいた」「こんなことができるようになった」という、気づきや変化のプロセスこそが成果として見られます。
中には、先輩の姿があまりに立派に見えて「自分は全然ダメだ…」と落ち込んでしまう学生さんもいます。
でも、それは誰もが通る道。知識不足や経験の少なさは“未熟さ”ではなく“伸びしろ”です。
実際に、以下の記事でもそのことについて詳しく触れています。
もし、自分焦ってるんだよね、という人はぜひ読んでみてください▼

成果発表では「何をやったか」だけでなく、「何を感じたか」「どう考えてどう変化したか」が大事。
その意識を持っておくだけでも、発表の質は大きく変わってきますよ。
発表テーマと実習の体験|成果のポイントは自分の気持ち
実習の成果が見えてきたところで、いよいよ本題に入っていきましょう。
この章では、画一的な「テーマの選び方」ではなく、
あなたが本気で語れるテーマを見つけるためのヒントを提供します。
印象に残った体験を洗い出そう|成長は体験からしか生まれない
実習中に印象に残った出来事は、今後の価値観を作る上で強烈な原体験になります。
かつて私が関わったある実習生は、
在宅医療で患者さんと話して、印象的だった。
薬剤師が患者さんのことを覚えていて、普段からすごく向き合っているのがわかった。
と語っていました。
印象に残ったということはそれだけ認識がひっくり返ったということ。
だからこそ、体験を振り返ることで、自分の成長が可視化しやすくなるのです。
実習前後の気持ちの変化に焦点を当てる|期待と現実のギャップ
実際に経験して「思ってたのと違った」と感じることもまた、大切な気づきです。
例えば「在宅医療を見たい!」と楽しみにしていたのに、実際は玄関先で薬を渡すだけ
…ということ、よくありますよね。正直、がっかりする学生も多いです。
逆に、興味がなかったことが体験してみたら面白かった、という場合もあるでしょう。
「調剤はただの作業だと思っていたけど、忙しい中で優先順位を考えて効率よく対応するのが、
意外にも自分に合っているとわかった」という学生も過去にいました。
そうした「思っていたこと」と「実際に感じたこと」のギャップも、立派な成果の材料になります。
マイナスイメージを切り口に|失敗は「成長」の母
そうはいっても「印象に残るようなことはそれほどなかった」という実習生もいると思います。
そんな方は、逆にマイナスイメージを切り口にしてみるのはどうでしょう?
「失敗して恥ずかしい思いをした」「指導された事に納得がいかなくてムカついた」など
こうした不快感はあなたの心が動いた証拠です。
もちろん、ただ愚痴っぽく話しても成果にはなりません。ですが、こうしたマイナスイメージの中には、
あなた自身や業界、その会社にとっての課題が潜んでいます。
課題を見つけて、そこに向き合い、改善の努力までできれば、
そこに向き合った時間は実習生にとってかけがえのない成長に繋がります。十分に実習の成果といえるでしょう。
ちなみに、自分の失敗をテーマに発表した学生の事例もあります。
詳しくはこちらの記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください▼
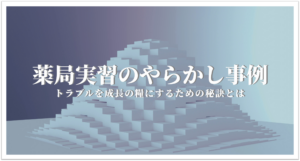
以上、実習の成果として本気で語れるテーマを見つけるためのヒントをお届けしました。
ポイントはいずれも自分の感情に目を向けるということですね。
さらに次の章からは、発表テーマを決めていくために注意すべき内容をお伝えします。
発表テーマを決める際の落とし穴|よくある失敗例とその理由
ここまで話したような「自分の気持ち」に焦点を当てたテーマ選びができないのはもちろんのこと
「成長が見えない発表」になってしまう実習生というのは実は少なくありません。
テーマ選びのヒントが分かった今、次は「これだけは避けたい、でもよくある失敗パターン」
を紹介します。
カテゴリでテーマを考えてしまう|誰でもできる調べ学習型
発表テーマを考える時、カテゴリから見つけ出そうとする実習生が多い印象があります。
確かに出会った患者の中から、一つの疾患や薬についてまとめればそれなりの構成が出来上がります。
でも、これでは実習を経験していなくても、誰でも書けてしまいますね。
こうしたケースでは、カテゴリから離れて一旦体験した事例に焦点を当てるか、
同じカテゴリの事例を複数あつめて比較してみるなどすると独自性がでてきます。
事例の報告になってしまう|体験をそのまま紹介するレポート型
あったことをそのまま話す事例報告型になってしまうケースもしばしば見受けられます。
もちろん、事例は相手に理解してもらうためにも必要です。
前章にも書いたとおり、テーマを考えるときには、
その体験を通して自分の気持ちがどう動いたかを丁寧に見ていくことが大切です。
このケースでは、話したい体験自体は決まっているので、そこに対して「自分がどう感じたのか」
「なぜそう感じたのか」「その経験が今後にどう活きるのか」まで考えを深めてみると、発表に厚みが出てきます。
感情が学びに昇華されていない|具体性に乏しい感想文型
逆に、感情は込められているけど具体性が伴わないケースもあります。
例えば、
患者さんとの関わりを通して、傾聴の大切さを学びました。
薬剤師がチーム医療の中核を担っていくべきだと感じました。
のように、よくありそうな理想論や具体性のない感想に終始してしまうケースです。
このパターンは、「言いたいこと」はちゃんとある状態なので、それを自分の体験と結びつけてあげることで、
伝えたいことが明確になって発表が引き締まります。
何度も言うように、実習の成果は「知識が増えた」ではなく、
「自分がどう変われたか」というところにあります。
そのため、テーマを決める際に重要なのは、自分が何を感じたのかという「価値観」と、
そこから一歩踏み込んで得られた「学び」の両方が含まれているということ。
それがなければ及第点すらあげられません。
テーマを決めるときは、自分なりの「価値観」と「学び」がちゃんと入ってるか、
最後にもう一度チェックしてみてくださいね。
成果発表のテーマ例|事例をもとに構成の考え方を解説
ここまでテーマ選びの考え方や、よくある失敗例を紹介してきましたが、
「とはいえ具体的にどう組み立てればいいの?」と感じた方も多いかもしれません。
そこでこの章では、実際に私が関わった実習生の事例をもとに、
発表テーマの組み立て方や私が当時指導した際のポイントを解説します。
発表テーマ例|発表の内容と流れを簡単に公開
以下は、ある実習生が作成した発表の構成例です。
テーマ:患者と薬剤師の関わり方について
1.実習を通して思ったこと
①患者にも色んな人がいる
②薬剤師が患者の顔や性格を予想以上に覚えている
2.在宅医療の実例2症例:
患者と話して印象的だったこと。考えて提案したこと。
3.実習を通して成長したと思うこと
①投薬に対して抵抗感が無くなった
②患者さんとの会話は楽しいものと気づいた
ポイントは、症例解説そのものではなく「関わり方」に焦点を当てた点です。
彼女自身が印象に残った部分=患者さんとのやりとりや薬剤師の姿勢、そこにテーマを絞り込んだことで“自分らしさ”が表れた発表になりました。
作成時に実習生が悩んでいた点|実習生のよくある悩み
実際、彼女も最初からうまくできたわけではありません。
初案の段階では次のような悩みがありました。
この状態は、3章で紹介した「レポート型」の典型例でした。
テーマ自体は決まっているのに、発表を聞く側からすると「で、あなたはどう思ったの?」が見えない。
そんな状態ですね。
私が伝えたアドバイス|自分らしさを引き出すために
そこで私が伝えたアドバイスは、次の2点でした。
たとえば彼女の場合、むくみのある患者さんに対して「利尿薬を使った方がいいのでは?」
と考えた場面がありました。
最終的には薬剤師から「患者さんの負担を考えて別の方法を検討しよう」とアドバイスを受け、
着圧パッドの提案にたどり着きます。
こうした経験は、ただ「教わった」だけではなく、自分なりに考えて意見を出したうえで得た学びです。
「自分ってこういうふうに考えてたんだ」「薬の作用だけでなく、患者さんの生活まで考えることが大事なんだ」と、新しい気づきにつながりました。
発表テーマ決めのチェックリスト|これだけ確認!
テーマが決まった!という人も、一度立ち止まって、以下のポイントを確認してみましょう。
これを押さえておくだけで、聞き手にちゃんと伝わる発表になります。
<テーマを決める6つのチェック項目>
1️⃣ そのテーマは「自分が本気で語れる内容」か?
→ 興味がないことや、誰でも言える内容になっていない?
2️⃣ 体験(事例)が必ず含まれているか?
→ 実習中に印象に残ったエピソードを具体的に紹介できている?
3️⃣ エピソードごとに「その時どう感じたか」を言葉にできているか?
→ ただ出来事を並べるだけではなく、自分の感情を添えている?
4️⃣ その体験を通じて「自分はどう変わったか・学んだか」が説明できるか?
→ 失敗や迷った経験も含め、成長のきっかけを語れている?
5️⃣ 発表の流れが「テーマ → 体験 → 気づき → 成長」で自然につながっているか?
→ 聞き手が途中で「結局何が言いたいの?」とならない流れになっている?
6️⃣ テーマやスライドタイトルに“自分らしい言葉”を使えているか?
→ 難しい表現や借り物のフレーズではなく、自分の言葉で語れている?
この6項目をチェックできたら、テーマ決めとしては合格ライン!
あとは実際のスライド作りや見せ方を整えていくだけです。
以上、発表テーマの決め方とチェックポイントをお伝えしました!
スライド作成の具体的なコツについては、以下の記事で詳しく解説しています。
是非こちらも確認してスライド作成に活かしてください▼
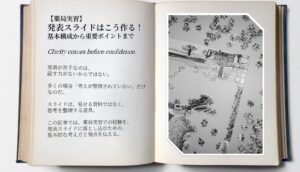



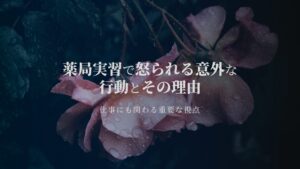

コメント
コメント一覧 (2件)
[…] 【薬局実習】発表テーマの見つけ方|現役薬剤師が語る実習の成果とは […]
[…] 【薬局実習】発表テーマの見つけ方|現役薬剤師が語る実習の成果とは […]