選挙なんて興味ないって思っていませんか?
正直、意味もわからないし、行っても何も変わらない。その気持ちはよくわかります。
実際、薬剤師や薬学部の学生の間では、選挙に行かないという人も少なくないようです。
だってめんどくさいから。
でも実は、薬剤師として働くうえで政治は極めて重要。知らないと結構マズイかも。
この記事では、医療と政治の関係性をわかりやすくひもときながら、2025年参議院選挙がどんな意味を持つのか、
そして自分にとって“推せる政党”を探すための考え方をお伝えします。
※各政党の是非は問いません。
未来を選ぶのは、今のあなたです。 まずは一緒に、考えるところから始めてみましょう。
医療と政治の関わり|薬剤師が選挙に行く意味はない?
政治ってよくわからないし、自分たちからは遠い存在な気がしますよね。
でも実は、私たち薬剤師の働く現場は、制度の上に成り立っています。
そしてその制度を決めているのが「政治」です。
こういった話題の背景には、必ず「どう制度を運営するか」という政治の判断があります。
制度が変われば、薬局のあり方も、薬剤師の仕事も変わります。
この先、AIが進めば調剤のあり方だって見直されるかもしれません。
その変化を「上から降ってきたもの」としてただ受け取るのではなく「自分たちの意思」
で選び取る。 そのために行うのが本来の選挙です。
そう考えれば、薬剤師にとっても関係ないことでは全くないと思いませんか?
今の政治の状況は?まずは政治の基本を解説
医療制度が政治で決まるって聞いたけど、そもそも「政治」ってどうなってるの?
という方も実は多いのではないでしょうか。
まずは基本的なしくみを3つの視点から簡単におさらいしておきましょう。
この章は基本の確認。
選挙があまりわからないという方はしっかり確認してもらうと理解が深まります。
衆議院と参議院の関係|参議院は薬剤師に似ている?
日本の国会には衆議院と参議院があります。2025年には参議院の選挙がありました。
参議院は任期が6年で3年ごとに半分が入れ替わります。
定員248人の内の124人(選挙区74、比例代表50人)を選びなおすのが参議院選挙。
参議院は衆議院に比べて任期が長く解散もないので、
長期的な目線で政策を実行することが出来ると言われています。
しかし、内閣の不信任決議権がないなどいくつかの点で衆議院より権利が弱く設定されています。
また「衆議院の優越」と言って、衆議院と参議院で意見が異なる場合、
衆議院で最終的に可決された内容が優先的に決定事項となります。
そんなわけで参議院は、衆議院の議決に対して審議し、場合によっては疑義を申し立てる
チェック機関としての位置づけが強くなされています。
こう考えると、我々薬剤師となんだか似ていますね。
※衆議院が出した法案を参議院が否決した場合も、衆議院で再度審議し2/3以上票を得られれば可決される。
与党と野党の違い|誰が政治を仕切っている?
政治ニュースでよく耳にする「与党」と「野党」とはなんでしょうか。
国会議員は色々な考えを持つ人たちが党という名のチームを作って活動しています。
その政党の分類がこの2つ。
・与党:今の政府(内閣)をつくっている側。現在は自民党と公明党の連立政権です。
・野党:別の意見や政策を示す側。与党以外の政党は全て野党といいます。
簡単に言えば、与党は“今の方向性を進める側”、
野党は“それにブレーキをかけたり、別の道を示す側”ということです。
勿論、野党から政策の案が出ることもありますが、政治には特に与党の影響が色濃くでます。
なぜなら、実際に政治を執り行う内閣は、日本では与党から選出されているからです。
そのため、与野党のバランスがどうなるかによって、日本の方針は大きく変わります。
政治で選挙が重要なワケ|選挙は“椅子取りゲーム”
さて、ではなぜ選挙が重要なのかというと、この与野党を決めるのが選挙だからですね。
国会には決められた数の議席があり、選挙でその椅子を政党が奪い合っています。
そして簡単にいえば「一番多い議席を持っている政党が内閣を組織し政治を行う」のです。
※法案や予算を審議する国会に対し、内閣は政治を実際に行う組織。
その内閣のメンバーは、与党が決めるのです。
国会では政策を多数決で審議します。
つまり、国会で議席を沢山持っていれば持っているほど、
政党の思い通りに政治を動かすことができるということです。
いかに選挙が政治を決めるベースになっているのかがわかりますね。
社会保障制度に関する公約を比較|各政党の公約を読み解くポイント
各政党は、外交や経済、安全保障などさまざまな分野で公約を掲げています。
でも、薬剤師や医療職として注目したいのは、やっぱり“社会保障政策”の部分。
年金や医療・介護、社会保険料など、日々の暮らしや働き方に直結する分野です。
ここでは、政党によって異なる「社会保障に対するスタンス」を3つの軸で比較してみましょう。
以下のサイトでは、より詳しく政策を比較することができます。参考にしてください。
内容の視点の違い|社会保障のどこに注目するか?
ひと口に社会保障といっても、その中身は多岐にわたります。
たとえば──
政党によって、どこに重きを置くかが大きく異なります。
高齢者向けの支援を強調する政党もあれば、少子化対策として子育て支援を最優先に掲げる政党もあります。
中には「現役世代の保険料負担を減らすこと」を軸に据えるところも。
つまり、どこを優先するか=どこにお金を多く配分するか、という話でもあるのです。
つらさ解決の手法の違い|「どうやって」支えるのか
すでに働いている読者の方なら共感してもらえると思うんですけど、
社会保険料って正直”重い”ですよね。
ということで、次に見たいのは、その制度をどう支えるかという手法の違い。
ざっくり言うと以下の違いです。
たとえば、医療や子育てに対して「現金を直接支給する」政党もあれば
「医療費の窓口負担を下げる」といった形で“利用時の負担軽減”を訴える政党もあります。
手法によって恩恵を感じる対象者やタイミングも変わってきます。
今なのか未来なのか。その視点も大事ですね。
財源の考え方|その負担、誰が担う?
当然ですが、社会保障を手厚くするには“財源”が必要です。
社会保険料を減らすとなれば、その分をどこかで補填する必要もあります。
ここで各政党の立ち位置がくっきり分かれてきます。
つまり、社会保障の裏側には「誰が、どこまで負担するか」という価値観の違いがはっきり出るというわけです。
こうして見てみると、社会保障に対するアプローチが政党ごとにかなり違うことがわかってきたと思います。
次の章では、こうした違いをふまえて「各政党がメインで訴えている公約」について見ていきましょう。
選挙の選び方がわからない|各政党のメイン公約と争点に着目
前章では各政党の社会保障政策に着目してみましたが、政党によって力を入れている政策の方面が異なります。
どの政党を選べばいいのか悩んでしまうのも無理はありません。
ここでは、選挙での「選び方」のヒントとして、2つの視点をお伝えします。
各党のキャッチコピーに注目|一番伝えたいことは何か?を読み解く
選挙になると、街中にズラリと貼られるポスター。
そこに並ぶ言葉たちには、各政党の「今伝えたい一番の想い」が詰まっています。
たとえば、2025年参院選当時の政権与党の自民党は「この国を動かす責任がある。」
公明党は「やると言ったら、やり切る。」をそれぞれ掲げていました。
一つの政策に限らず全体を運営している与党だけに、
キャッチコピーは抽象度の高いものとなっています。
一方、野党はテーマがわかりやすいものも多いです。
などはそれぞれの主張と力を入れている政策が一発でわかりますね。
※すべての政党を網羅できていません。政党の紹介がテーマではないので悪しからず。
こうして見ると各政党がどんなテーマを主軸に据えているかが見えてきます。
それは「自分たちは何を優先したいのか」というメッセージに他なりません。
まずはキャッチコピーを入口に「どんな未来を描いているのか」に注目してみましょう。
“その時”によって変わる選挙の争点|政治と社会の関わり
選挙ごとに、政治の世界で話題になるテーマ(=争点)も変わります。
たとえば、新型コロナが流行した2022年は「医療体制」「経済支援」が主な争点でした。
2025年の参院選では、たとえばこんなテーマが争点になっていました。
※もちろん、これだけではありません。あくまでも一部です。
どれも当時「今まさに話題になっている」ことばかりでした。
たとえば“米の供給”なんかは、ニュースでも毎日のように取り上げられていました。
つまり、選挙の争点は“自分たちが今どんな問題に直面しているか”で変わっていくのです。
今、自分が一番不安に感じていることは何か。そこに目を向けることで、
「どの政党が自分の代弁者になりそうか」が見えてくるかもしれません。
選挙はゲーム|戦略と周りの動きがポイント
ここまでで、各政党の政策や争点について理解が深まったかと思います。
でも、いざ投票となると「どこに入れればいいの?」と迷いますよね。
そこで最後は、選挙を“戦略”として考える視点をお伝えします。
議席数と政治のバランス|“大きな力”か“多様な声”か?
政治は多数決で決まるので、議席数が多い政党ほど意見を通しやすくなります。
与党(自民・公明)が過半数を占めている状態だと、政権運営はスムーズ。
反面、これは与党の思い通りに法案が通りやすいということでもあります。
逆に色々な政党が議席を持つことは、多様な視点から議論される機会も増えるというメリットがあります。
つまり:
このどちらを重視するかが人によって考えが変わるところです。
“票の活かし方”とSNS活用
政治と議席数のバランスを考えると、選び方には2つの考え方が出てきます。
自分の望む政策を掲げる政党に入れるのが望ましいのは事実ですが、
現実問題として、支持率が高くなければそもそも選挙に通らない可能性もあります。
選挙は票を多く貰った人が通過する”ゲーム”だから。
そこで、支持が集まりそうな人や政党を選ぶことで、議論の余地を生むことを目的にする。
これも一つの戦略と考えられます。
2025年の参院選では各政党ともSNSを利用しており、盛り上がりを見せていました。
これらの情報から支持層を見極めるのもゲームとしての楽しみ方になります。
参院選ならではの投票方法|比例代表を活用しよう
参議院選挙は、以下の2つの票で結果が決まります。
選挙区は地域の候補者に投票します。
一方、比例代表は全国区の候補者か政党名を選ぶシステム。
政党名なら政党内の優先順、候補者名ならその人への直接票として扱われます。
なるべく人名で投票した方がみんなに選ばれた代表が国会に入るという形ができますね。
ちなみに比例代表では、地域の選挙区に候補者がいない政党も選ぶことが出来ます。
候補者が少ない政党を応援するなら比例代表で票を入れるのも一案ですね。
以上、選挙のシステムと今回の参議院選挙について説明しました。
どこに投票すればいいか迷う…という方は、
「みんなの選挙 選挙ナビ(JAPAN CHOICE)」も参考にしてみてください。
政党ごとの主張や政策が一覧でわかる診断ツール付きです。
※外部サイトに飛びます。
まとめ|薬剤師・薬学生も未来のために選挙にいこう
以上、選挙の基本について解説しました。参院選に注目が集まっているので、政治の話としました。この記事の内容を以下にまとめておきます。
・薬剤師の仕事と政治は密接に関係している
・政治は多数決であり、選挙はその議席を奪い合う椅子取りゲームである
・医療に特に関係する社会保障の考え方も政党によって異なる
・政党が訴えている中で各政党のメインとなる政策から選ぶのも一案である
冒頭に書いた通り薬剤師にとっても政治は密接に関係しています。
今回に限らず政治にはしっかり向き合っていきましょう。
未来は今の若い人のためにあるのですから。
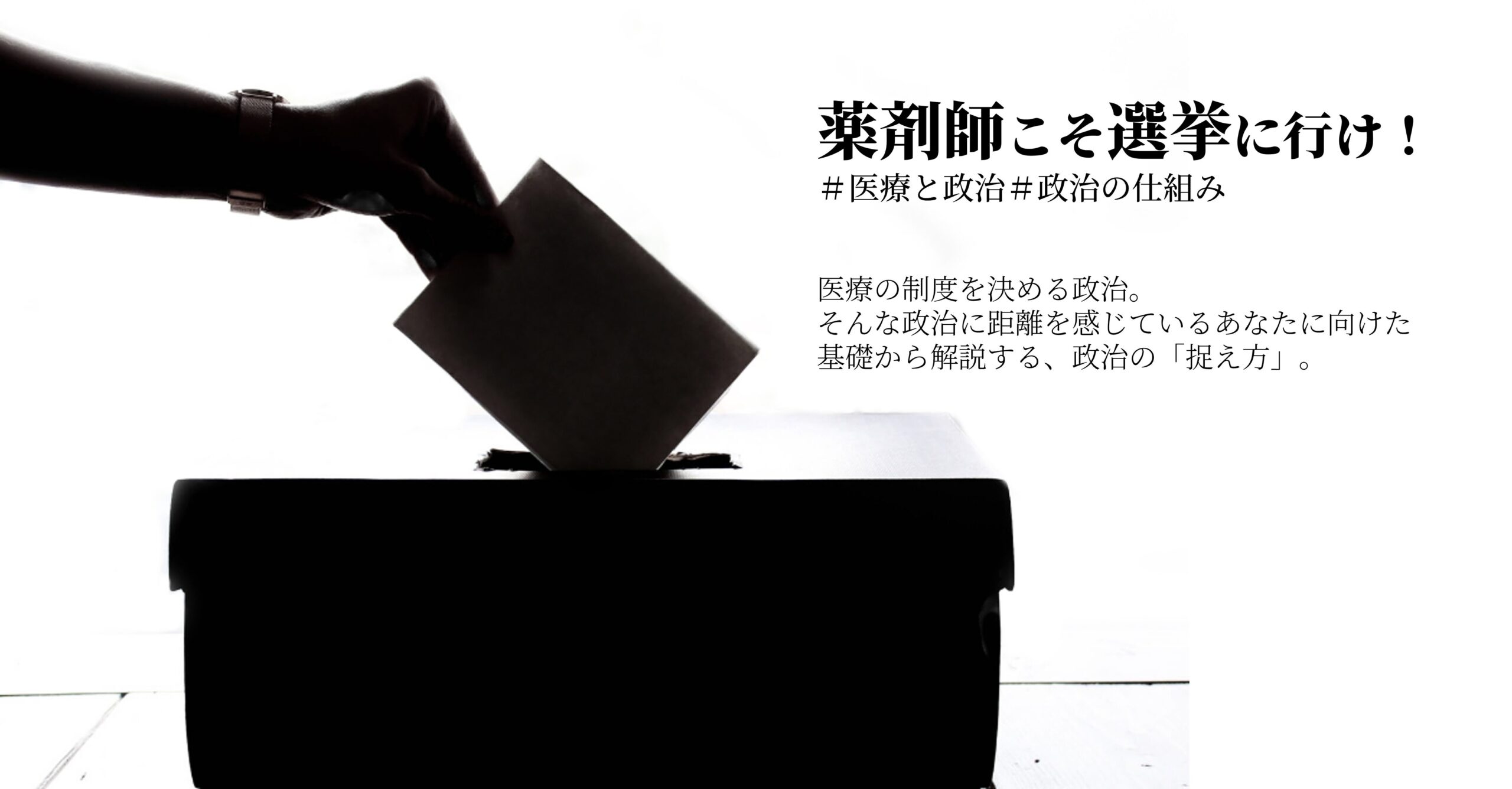

コメント