「今日も指導薬剤師の質問に答えられなかった……」
「勉強したはずなのに、全然思い出せない……」
CBTを乗り越えて臨んだ薬局実習。だけど現場に立ったとたん、自分の知識不足を痛感する。
これは、多くの薬学生にとって“あるある”の光景です。
それでも、何度も答えに詰まったり、他の実習生との差を感じたりすると次第に自信を失ってしまうことも。
薬局実習は、学生のうちに“生きた現場”と向き合える貴重な経験。
だからこそ、その時間を「できなかった」で終わらせるのではなく、
「学びきった」と胸を張って振り返ってほしい。現場の薬剤師としてはそう思います。
本記事では、実習の経験をただの“消費”で終わらせず、自分の血肉に変えていくための——
「勉強の思考法」について解説します。
もっと実習前に勉強しておけば…|誰もがぶつかる知識の壁

私が関わってきた多くの実習生には、棚にある薬の薬理作用はもちろん、疾患のメカニズムや
製剤的な特性、法規的な知識に至るまで、クイズ形式で日々問いかけて答えてもらっていました。
その経験から言って、基本的に実習に来る段階では、ほとんどの学生がそれまでに学んだ内容
なんてほとんど覚えていません。
もちろん、知識が豊富で優秀な学生もいます。
だけど、そんな子でさえ「問題は全部わかるし、実習で学ぶことが一つもなかった」
なんてケースは一人もいませんでした。
「もっと実習前に勉強しておけばよかった」
そう口にする学生も少なくありませんが、そもそも“忘れているのが普通”だということを、
まずは知っておきましょう。
時には怒られることも?実習をしんどいと感じる原因の1つが「知識不足」

とはいえ、実習を行っているのは“現場”です。
忙しい時もあるし、余裕がない場面だってたくさんあります。
おまけに、薬剤師は教員ではありません。
教えるのがド下手くそな人もいれば、コミュニケーションすらまともに取れない指導薬剤師も
世の中にはいます。それが現実です。
かつて、私がいた会社の他店舗で実習していた学生も、
指導薬剤師から「知識がなさすぎる」と匙を投げられ(※物理的にではない)、
落ち込んでいたのを見たことがあります。
なにより知識がないと、患者さんへの指導ができないという実感も湧いてきます。
知識不足によって迷惑をかけてしまうかもしれない。
そう思えば、焦るのも無理はありません。
では、実習で知識不足を痛感したとき、どうやって追いつけばいいのでしょうか?
次の章からは、実習の経験を「自分の学びに変える」ための思考法について解説していきます。
勉強の目的地|薬局実習の”ゴール地点”でどうなっているべきか

では、実習中にはどんなことを意識して勉強していけばよいのでしょうか?
膨大な知識を習得する必要のある薬学部において、短い実習期間中にすべてを振り返るのは
現実的ではありません。
だからこそまずは、実習を終えた時点で「どのくらいの知識レベルになっているのが理想なのか」──この“ゴール感”を明確にしておきましょう。
目指すは教科書レベル|知ってる薬の基本をきっちり
最初の目安は、「教科書レベルの内容を説明できる薬があること」。
全部の薬を網羅する必要はありません。実習先で多く取り扱う主要な医薬品、
つまり自分の“触れた薬”だけで十分です。
まずは、それらの薬について、基本事項をきちんと押さえておきましょう。
薬局でよく出る薬は、門前の診療科や処方医のクセによって大きく変わります。
同じ科でも、医師ごとに処方のスタイルが異なるため、店舗が変われば薬剤師でさえ
一から学び直すこともあります。
つまり、“その薬局で多く出た薬”をマスターすることが、そのまま“得意分野”になります。
実習後、「この薬のことなら自分に聞いてくれ」と言える状態になっている。
そんなイメージです。
何が分からないかが分かる|調べる力の第一歩
二つ目の目安は、「自分が何を分かっていないのかを自覚できていること」。
分からないことが多すぎると、何が分からないのかすら分からず、
調べることも、人に聞くことも難しくなります。
実際、説明してもその都度つまずいてしまい、話が進まない学生も過去にいました。
逆に、「○○が分かっていない」「この点を理解すれば解決する」といった視点があれば、
自分で調べることができますし、人に質問する時も明確に伝えられます。
「分からないことが分かる」というのは、調べる力の原点です。
成長を客観視する意味でも、この状態に到達していることは重要な一歩です。
経験を言語化できる|頭の引き出しに“ストーリー”を刻む
三つ目は、実習の経験を言語化できるようになっていることです。
これは知識レベルというより、記憶の定着度を高める“土台”に近い話。
暗記に最も必要なのは、ストーリー。
人間は、ただ文字情報として記憶するよりも、ストーリーと結びついた情報のほうが
圧倒的に覚えやすくなります。特に「感情が動いた体験」は記憶の定着率を飛躍的に高めます。
薬の名前や作用は後からでも調べられますが、患者さんとの会話や悩んだ経験は
“その時”しか得られません。だからこそ、自分が見聞きしたこと、感じたことを言語化し、
頭の中に“経験の引き出し”をつくっておく。これが後々、大きな力になります。
以上、実習の終わりに到達していたい知識感について解説しました。
「え、意外とシンプルじゃない?」と思った方もいるかもしれませんが、
実はこれらを意識するだけで、実習がまったく違ったものになります。
次章では、こういった“知識の地盤”をつくるために、どのような勉強スタイルを持つべきか。
具体的な方法論に踏み込んでいきます。
薬局実習中にすべき勉強|机の上とは違う、現場の学び方

いよいよ、実習中に「どうやって勉強すればいいのか?」に迫っていきます。
少し実践的な内容になりますが、実際に私がこれまでの実習生にやってもらってきた方法です。地道に続ければ、必ず身につきます。
1つの薬に知識を紐づける|目の前の薬から広げよう
実習の大きな価値は「本物の薬」に触れられること。
これだけで、机上の勉強とはまったく違った刺激があります。
例えば、ランソプラゾールOD錠。
薬理作用がPPIとわかっていれば十分…ではありません。
以下のように、これまで学んだ知識を紐づけてみてください。
・どんな疾患や症状に使われる?(病態)
・化学構造と作用機序の関係は?(化学)
・OD錠ってどういう製剤?(製剤学)
・保管方法や規制区分は?(法規)
・噛んでもいい?普通に簡易懸濁していい?(実務)
課題ドリブンの思考|患者と処方から学ぶ
薬を起点にするだけでなく、症例から考えるのも強力な方法です。
たとえば、患者さんとの会話、処方内容、薬歴を思い出しながら…
・何に対して、この処方?
・うまくいかなかったら次は何を考える?
・副作用が出たらどう対応する?
こんなふうに、「今ある情報から何が読み取れるか?」を考えるクセが大切です。
これは「課題ドリブン思考」とも言われる手法。
机での積み上げ式学習とは違い、“問題に対して答えを探す”というリアルな学び方になります。
少し難しく感じるかもしれませんが、現場でこそ得られる力です。
思い出すことから始める|復習ハードルを下げよう
人間は1日経つと学んだことの約7割を忘れると言われます。だから復習が大事
…とはいえ、実習中は毎日ヘトヘトでそんな余裕ないですよね(笑)
そんな時は「思い出すだけ」でOK。帰り道やお風呂の中でいいので、
・関わった患者さんは何を言ってた?
・薬剤師に何を教えてもらった?
を思い返してみましょう。
“復習しなきゃ…”ではなく、“思い出をなぞる”つもりでやると気楽に続けられます。
さらに、思い出す中で「わからなかったこと」が出てきたら、
それをメモだけでもしておくと◎。
調べる元気がある時にまとめて調べればいいのです。
ちなみに、私が関わった実習生には、 毎朝こう聞いてました。
「ねえ、昨日勉強した内容、教えて?(ニコッ)」
……え?やだなあ。かけてませんよ?圧なんか(笑)
実習を楽しいに変える考え方|「できない」は伸びしろ

ここまで、薬局実習中の勉強法や知識の捉え方について解説してきました。
正直なところ、知識不足に悩むと「自分は向いてないんじゃないか」と感じてしまう
人もいます。でも、それはまだ“楽しさ”を見つけられていないだけかもしれません。
最後に、「知識が足りない自分でも、実習を楽しく感じられる方法はあるのか?」
という問いに向けて、少しだけ視点を変えてみましょう。
人が楽しいと感じる5つの感情|自己理解を深めよう
仕事や勉強において、人が「楽しい」と実感する瞬間は概ね以下の5つの感情に集約されます。
・できなかったことができるようになったことを実感したとき(成長実感)
・他の人よりも秀でていることが分かった時(優越感)
・顧客や周囲の人から感謝されたとき(承認感)
・物事を一段深く理解したとき(洞察感)
これらの感情は、どれが自分にとって最も心地良いかで“楽しい”の感じ方が変わります。
たとえば「達成感」が大事な人は、何か任された時に達成を目指して行動すると楽しいと感じやすく、「承認感」が強い人は患者さんからのありがとうが大きなモチベーションになります。
まずは、自分がどんな時に「楽しい」と感じるのかを思い出してみてください。
それだけでも、実習の中で自分なりの“楽しさ”を見つけるヒントになるはずです。
学生は学ぶ立場|「できるようになる努力」に集中しよう
知識不足で落ち込むのは当然のことです。
でも、ここまで読んでくれたあなたなら、もうわかっているはず。
実習は「できない自分」を責める場ではなく、「できるようになる努力をする場」なのです。
そもそも完璧な知識を持っている学生なんていませんし、私たち薬剤師ですら知らないこと、
調べながら仕事をしていることもたくさんあります。
実力を証明する場所ではなく、“伸びしろ”を見つけて磨く場なんです。
ただしひとつ、気をつけたいことがあります。
実習は「受け身でいれば何かを与えてもらえる」ものではありません。
自分から動いて、吸収していくための場です。
これは単なる知識の話ではありません。たとえば、指導者の話を素直に聞く姿勢、
患者さんと良い関係を築こうとする気配り、積極的に関わろうとする勇気。
そういった“人としてのあり方”も、実習の中で少しずつ育っていくのです
とはいえ、実習の環境には運や相性もあるのが事実です。
「誰に当たるか」で体験が大きく変わることもあります。
でも、どんな環境でも「自分の中で楽しさを見つけていく視点」はきっと役に立ちます。
「できない」は、まだ伸びる証拠。
あなたの中に眠っている“楽しいのタネ”を、少しずつ育てていきましょう。
もし今、知識に不安を感じていたとしても、大丈夫。
それは、誰もが一度は通る道であり、
あなたにも、きっと“自分なりの成長”が見えてくるはずです。
まとめ|実習では知識不足を恐れず成長しよう
以上、実習中の勉強について解説してきました。最後に今回の内容を以下にまとめます。
・「何がわからないか」を明確にし、調べられる力を養うことが次の学びに繋がる。
・経験を言語化することで、知識は“自分だけのストーリー”として脳に定着する。
・1つの薬や1つの症例から、横断的に知識を紐づける勉強法が、現場で役立つ思考力を育てる。
・できないことは“伸びしろ”。自分の成長を楽しむ姿勢が実習の価値を最大化する。
繰り返しになりますが、実習の限られた期間は本当に貴重な経験です。
不安もあるかもしれませんが、それも含めて“学びの一部”。
楽しく学んで糧にして、就活や国家試験、そしてその先の薬剤師人生に活かしていきましょう。
実習中の失敗に悩む人向けの記事も書いてます。
他の実習生の事例も載せているので是非読んでください!
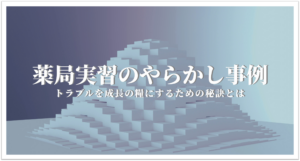



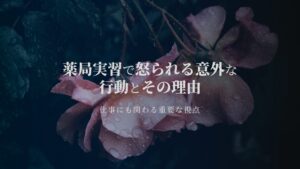
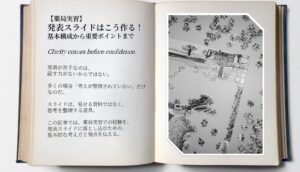
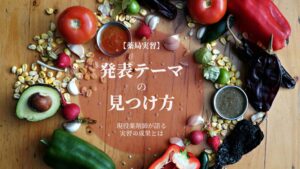

コメント
コメント一覧 (5件)
[…] 【薬局実習】知識不足に焦る君へ|実習を血肉に変える勉強の思考法 […]
[…] 【薬局実習】知識不足に焦る君へ|実習を血肉に変える勉強の思考法 […]
[…] 【薬局実習】知識不足に焦る君へ|実習を血肉に変える勉強の思考法 […]
[…] 【薬局実習】知識不足に焦る君へ|実習を血肉に変える勉強の思考法 […]
[…] 【薬局実習】知識不足に焦る君へ|実習を血肉に変える勉強の思考法 […]