初めてのことを行うときに失敗してしまった経験は誰しも一度はあるはずです。
こと実務実習では、たとえそれまで順風満帆にやってきた優秀な学生といえども、
やはり何等かのトラブルを経験するものです。
事の大小に限らず失敗し、さらに怒られてしまうと、萎縮してしまうこともあるかもしれません。
本記事では、これまでたくさんの実習生指導に関わってきた私が、
実際に見てきた実習生の失敗談をご紹介します。
また、失敗に対して落ち込んでいる皆さんに向けて、失敗をどんな風に捉えればよいのか、
その姿勢について現場の薬剤師の立場からお話しします。
やらかした!実習生の失敗珍事例3選
まずは、実際に私が見てきた実習生の“やらかし”エピソードを紹介します。
実習中の皆さんなら、もしかしたら「あるある!」と思うものもあるかもしれませんね。
ドライシロップをシロップと勘違い
私が当時在籍していたのは、小児科門前の薬局。
そこではシロップ剤を自動で分注できる機械(分注機)を使っていました。
処方内容を入力すると、適切なシロップボトルを選んでセットするだけで、
機械が必要量を自動で分注してくれるという便利なものです。
実習に来ていたAさんは、テキパキと動いてくれる頼もしい存在でした。
ある日も処方箋を確認して、すぐに分注機の前へダッシュ。でも、いつまで経っても機械が反応しません。
それ、ドライシロップ(粉)なんだよなぁ…
心の中でそう思いながら様子を見ていると、
Aさんはもう一度処方箋を確認しに戻り、ようやく気づいたようでした。
待機時間、約3分。気づきの速さはさすがです。
分包機の分包紙交換でエラー
粉薬を小分けする分包機。
フィルム(分包紙)が切れたときは、新しい紙に交換する必要があります。
当時の職場では、古い紙の終わりと新しい紙の始まりをセロハンテープで接続する方法を使っていました。
何度かやり方を教わったBさんが、ついに一人でチャレンジ。
セッティングが終わり、スイッチをオン!……した直後に、機械からは無情なエラー表示。
分包紙は半分に折りたたまれていて、片側が開いた状態で粉薬を入れる構造になっています。
その開いた側を、Bさんはうっかりセロテープで塞いでしまったのです。
紙がスライドするときに機械の内部で詰まってしまい、エラーに。
あわや大トラブルでしたが、すぐに相談してくれたおかげで事なきを得ました。
患者さんからの怒られ事例
Cさんが患者さんにお薬をお渡ししていたときのこと。
保険証とおくすり手帳を返却し、患者さんが小さなカバンにそれらをしまっている最中のことでした。
「この薬なんですけど……」
と話しかけたところ、
まだしまってる途中だろうが!!話しかけるな!!
と突然の剣幕で怒られてしまいました。
サポートに入っていた薬剤師も驚くほどの勢いでしたが、患者さんの状況をよく観察し、
声をかけるタイミングに気を配ることの大切さを、身をもって学ぶ機会になったと思います。
かくいう私も…|現役薬剤師・花炎の”今だから言える”やらかし経験
こんな実習生たちを間近に見て、微笑ましく佇む私ですが、自分にも実習生だった頃はあるわけで。
今だから話せる自分自身のやらかしも、ちょっとだけご紹介しましょう。
病院実習で”寝落ち”したあの日
薬剤師、医師、検査技師などが集まる院内チームのミーティングに参加したときのこと。
そのミーティング中に……寝落ちしました(笑)
薬剤部長と学校の教員の両方からしっかり怒られたので、結構な問題だったんだと思います。
……一応、言い訳ですけれども。
その病院は家から遠くて毎朝早起き、夜は課題に追われて寝不足。そりゃあ眠くもなります。
しかもそのミーティング、先生たちが見づらい画面を共有して、ボソボソと話しているだけ。
私たちは壁沿いの席で何も見えない・聞こえない・スマホも触れない。
はっきり言って「これ、意味ある?」という時間でした。
勿論、実習は忙しい仕事の片手間に行っているもの。
「実習”させてやってる”んだから真面目に聞け」と言われれば確かにその通り。
でも、今の立場で言わせてもらうなら……
しょーもない実習企画してんじゃねえよ
という気持ちが正直なところです(逆ギレ)。
…冗談はさておき、実習生は次世代の教育ですから、
寝落ちするくらい眠い設計にしてしまってはそれこそ時間の無駄というもの。
仕事の方が優先なのはもちろんですが、こういう場合、
指導者は実習の設計そのものを見直すべきではないかと思います。
真面目なのに態度面で怒られる
自分ではそこそこ真面目な性格だと思ってるのですが、態度面で注意を受けることも何度かありました。
薬局実習のとき、在庫検索のやり方を教えてもらったので、
手が空いたタイミングで誰も周りにいないのを見計らって、PCを開いて見てみたんです。
……が、まさかの雷が落ちました。
会社のPCは機密情報も多く、勝手に操作するのはNG。
今となっては当たり前の話なんですが、当時は「教えてもらった=やっていい」だと思っていたんですよね。
確認を取るって、大事。
身に染みて学んだエピソードです。
怒られる実習はつらい|失敗が導くさらなるトラブル
どんな実習生でも失敗はするもの。怒られる経験だって、決して珍しくありません。
でもやっぱり、怒られると落ち込んでしまいますよね。
この章では、「怒られたときにどんな気持ちになるのか」を整理した上で、
どういう心構えでいればいいのかを解説していきます。
以下の記事では実習で怒られる事例やその理由について詳しく解説しています。
怒られる理由を詳しく理解したい方は詳細を確認してくださいね▼
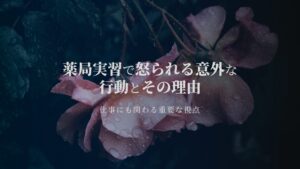
怒られた後に感じる反応を言葉にしてみる
まずは、人が怒られたときに抱く気持ちを整理してみましょう。
感情の向きが自分(①)、相手(②)、物事(③)の3方向に分かれるとすると、以下のようになります。
①自分に対する期待外れ感→落ち込む
②相手に対する反発心→イラっとする
③内容への再考→指摘を反芻する
多くの人は、①か②をまず感じるのではないでしょうか。
とくに、一度目の指摘では気にならなくても、再度注意されるとムッとくる。
「わかってるけど、うまくできないんだよ!もう!」みたいな。
本来は③のように「内容そのもの」に向き合うのが理想ですが、
言われ方や雰囲気なども関係するので、これはある程度仕方ないことです。
ちなみに私も、いまだに指摘されるとムッとすること、あります(笑)
だからこそ、「そう感じることは自然なことなんだ」と受け止めておくことが大事です。
失敗について考える|上手くいかないときのコミュニケーション
落ち込んだり、ムカついたりするのは当たり前。
その上で、成長するためには、物事の本質に目を向ける必要があります。
では、失敗をどうやって“糧”にするか?考える手順を3ステップで整理してみましょう。
1)原因を考える
まずはこうした視点で、「なぜうまくいかなかったか」を振り返ってみましょう。
2)原因ごとの対策を考える
3)コツを聞く
これができる人、意外と少ないです。
できないことは、できる人に聞く。それが上達の近道です。
でも、「何ができないのか」を自分で整理できていないと、質問しても効果的な答えは返ってきません。
だからこそ、1)、2)で原因を明確にした上で、「普段どうしてますか?」と聞くのがベストです。
実習期間中は、自分より上の人に気軽に質問できる“ボーナスタイム”。
これを活かせるかどうかで、成長スピードは大きく変わります。
失敗も経験のうち|失敗を成長に変えた”超優秀な”実習生の事例
ここまで実習中の“やらかし”や、その受け止め方について紹介してきました。
もし読んでくれている薬学生の皆さんが「あ、自分だけじゃないんだ」と少しでも安心できたなら、
それだけでもこの記事を書いた価値があります。
最後に紹介するのは、私がこれまで関わってきた中でも、
「失敗を成長に変える力がずば抜けていた」と感じた実習生のエピソードです。
私が関わったある実習生|印象的だった能力とは
本人いわく、大学内での成績は“中の上”くらい。
落第もなくストレートで国試にも合格しており、真面目に勉強するタイプではありましたが、
実習当初から特別に薬の知識が豊富だったわけではありません。
ただ、明るく元気で、人とのコミュニケーションがとても上手な方でした。
薬局内のスタッフ全員と自然に打ち解け、
実習終了時にはなんとスタッフ一人ひとりに手紙を渡してくれました。
そんな彼女が他の実習生と違っていたのは、知識量や処理能力ではなく、発想力でした。
実習の成果発表|失敗談に基づく「ヒヤリハット」
彼女の大学では、実習の最後に成果発表を行うことになっていました。
薬局側でも最終週に発表の場を設け、学生に発表してもらっています。
多くの実習生が選ぶのは、「自分が担当した症例」や「調剤した薬の分類」など、無難な内容です。
正直に言えば「患者の背景にどう向き合ったか」まで踏み込んで語る学生すら、ほとんどいません。
そんな中で、彼女が選んだテーマは「ヒヤリハット」。
しかも、それは自分の失敗体験をもとに組み立てられていました。
プレゼンを一緒に作っていく中で、彼女が“考える薬剤師”になるだろう、と確信させる内容でした。
そして「これはきっと誰かの気づきになる。」そう思えたことが、こっちまで嬉しくなるような発表になりました。
失敗を成長の糧に|実習生が経験した成長のための思考法
──それは、たった一つの失敗から始まった気づきの連鎖でした。
彼女の発表のきっかけになったのは、調剤中のちょっとした事故でした。
散剤を量っていたとき、手がすべって薬匙を調剤台の隙間に落としてしまったのです。
落ちた薬匙は、薬品棚の裏へ転がってしまい、取り出すのに一苦労。
「このままじゃ危ないよね」と話し合い、
彼女は隙間に段ボールで簡易のバリケードを作るという対策をとりました。
薬剤師さん達も、意外と小さなミスをしてることに気づいたんです
そう話す彼女は、そこから「なぜそれが問題にならないのか?」と考えるようになります。
その答えは、“ミスが起きる前提で、対策がとられているから”。
「鑑査って、“間違わないようにする”ためじゃなくて、
“間違いを前提にミスを拾う工程”だったんだって気づいたんです。
それは、自分が失敗をしやすいタイプだからこそ、本当に目からウロコでした」
彼女の成果発表は、
・自分の失敗の分析
・失敗に対する現場の対応の観察
・その意味づけを自分なりの視点で再構築
という3つを行い、それを学校で学んだ「ヒヤリハット」という知識と繋げていく、
素晴らしい思考プロセスに満ちたものでした。
一つの失敗から、ここまで深く思考を広げられる実習生は、そう多くありません。
その姿勢こそが、失敗を糧にする力なのだと思います。
まとめ|やらかし上等!実習を成長の場にするためのポイント
以上、実習のやらかしについて語ってきました。
最後に、この記事全体を通して伝えたいことを、もう一度まとめておきますね。
・実習中の“やらかし”は誰にでもあることで、珍しいことではない。
・怒られたときの感情は自然な反応。大切なのは、そのあとにどう向き合うか。
・失敗の原因を冷静に振り返ることで、自分なりの改善の道が見えてくる。
・実習は、自分より経験のある人に直接コツを聞ける“成長のチャンス”でもある。
・成長とは、知識やスキルよりも、「失敗をどう受け止めるか」という姿勢に表れる。
勉強しに行っているのだから、失敗するのは当然のこと。
むしろ、「できないことをしっかり受け止めて、どう向き合うか」が何よりも大切です。
そして、やらかしを最小限に留められるよう、
実習生を見守るフォローは、指導者にとって大切な役割のひとつです。
もしこの記事を読まれていて「指導って難しいな…」と感じている指導者の方がいれば、
こちらの記事もぜひ読んでみてください。

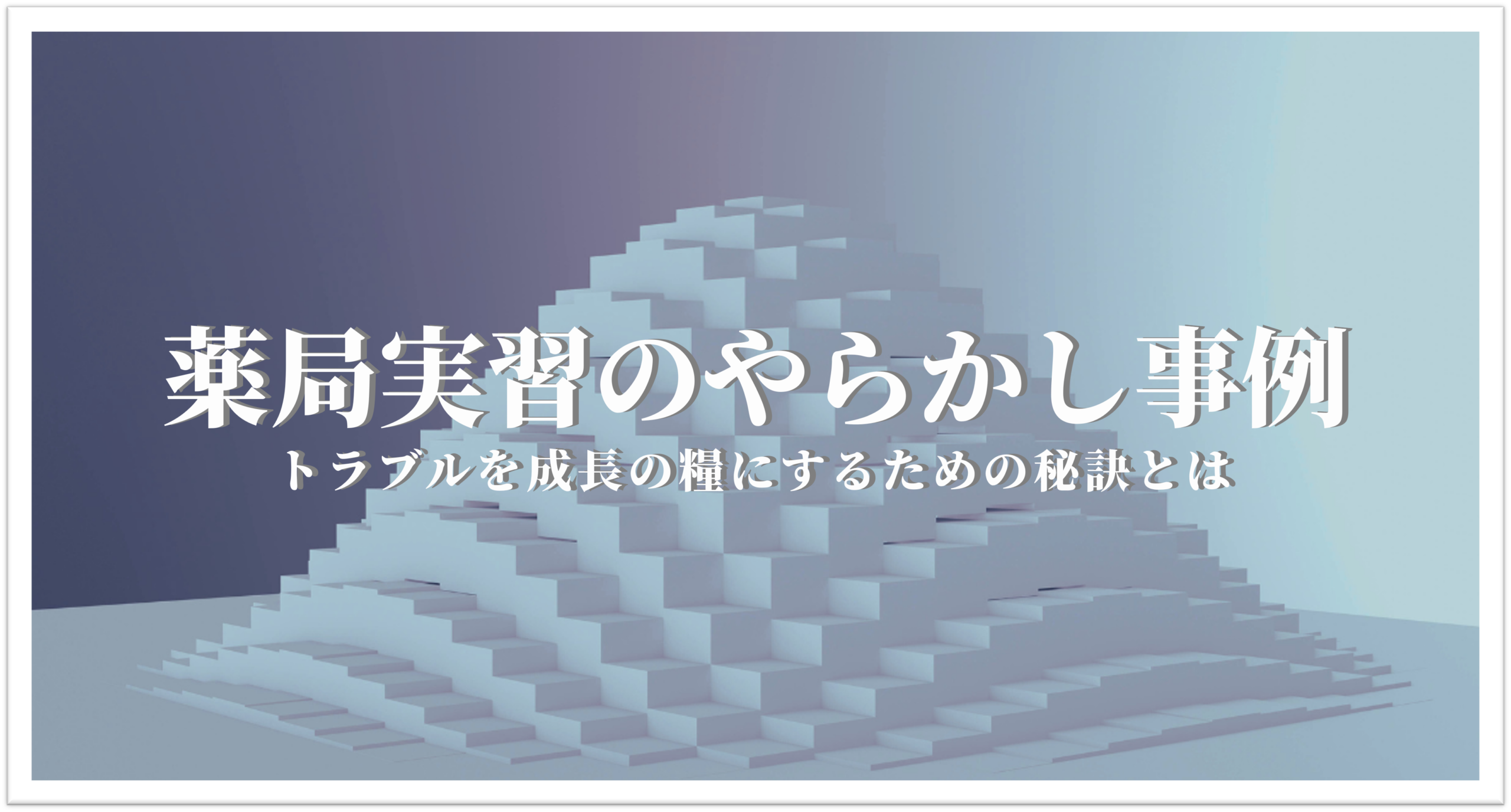


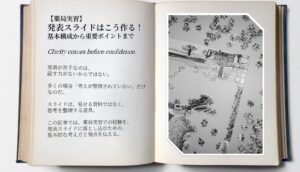
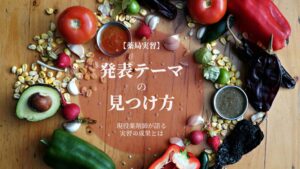

コメント
コメント一覧 (3件)
[…] 薬局実習のやらかし事例|トラブルを成長の糧にするための秘訣とは […]
[…] 薬局実習のやらかし事例|トラブルを成長の糧にするための秘訣とは […]
[…] 薬局実習のやらかし事例|トラブルを成長の糧にするための秘訣とは […]